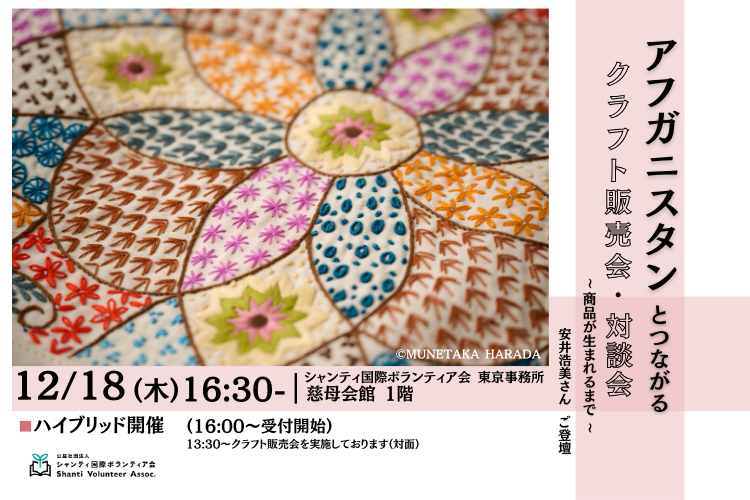【開催報告】シャンティ国際ボランティア会 「コロナ以後の地域社会を考える ~宗教とNGOの視点から~」
シャンティは、多くの関係者やご支援者の方々に支えられ、設立40年目を迎えました。設立時より曹洞宗僧侶の皆様を始め、宗派を超えて全国の寺院、僧侶、寺族の方々のご支援とご協力をいただき、これまでアジアの8地域で教育文化支援、緊急人道支援を続けてまいりました。
2021年3月25日(木) にシャンティ国際ボランティア会 2021年度総会にあわせて、「コロナ以後の地域社会を考える~宗教とNGOの視点から~」と題し、オンラインイベントを開催しました。
当日のイベントの様子は、以下よりご覧いただけます。
ご挨拶
対談に先立ち、曹洞宗宗務総長鬼生田俊英様よりご挨拶をいただきました。
曹洞宗宗務総長 鬼生田 俊英 様
私は有馬さんと最初にお会いしたのは20歳代でございまして、当時集団就職というのがあり、もうそういうことをご存じの方はいないと思うのですが、当時就職列車というのがございまして、私の在住は郡山でございますが、郡山から夜行列車で8時間かかって、上野に着き、それから就職先の事業主が各々迎えに来て、
職業に就いて、戦後の経済復興を成し遂げた一番の根幹はその辺にあるのではないかと思います。私はまだ子どものことでしたが、お母さん、お父さんが幼気な、中学校を卒業したばかりの子どもを、見知らぬ東京に出してやるということに涙ぐんで、送り出してやったのでございます。
それでもその当時、そういう幼気な子どもたちの力になろう、若い者の根っこの力になって、若い者の根っこでもって日本を復活しようという、有馬先生の大きな情熱があったような気が、私は今になって思うところでございます。
まず、シャンティ国際ボランティア会様が、活動40周年を迎えられましたことに対し、心よりお祝い申し上げます。
シャンティ国際ボランティア会様と曹洞宗とでは、慈悲行・菩薩行の実践を通じ、人々の救済を推進し社会に寄与するため、2019年相互協力協約書を取り交わしました。今後とも自然災害の多発する日本において、より強固な協力関係が築けますことを願う所であります。

続きまして、シャンティ会長の若林恭英よりご挨拶申し上げました。
シャンティ国際ボランティア会会長 若林 恭英
島薗先生は、宗教学者として、宗教、仏教者の社会に対するありよう、ということについてご発言をされておりまして、かねがね我が身を振り返るようにさせていただいております。
無縁社会という言葉に代表されるように、孤立・偏見・差別が社会に蔓延する今、我々がどのような連携し行動していったらよいのか、「共に生き、共に学ぶ」平和な社会実現に向けて、ご示唆を頂ければと存じます。
大菅専門アドバイザーには、企画から、けん引、今日に至るまで、色々と細々と引っ張っていただきまして、誠にありがとうございます。

映像上映「地域から描く、地球市民社会の地図~若林恭英~」
シャンティは設立以来、曹洞宗に限らず地域社会の拠点である、全国のお寺や教会など宗派・宗教を越えた宗教界の皆様、各地域の皆様にお力添えをいただいております。故有馬実成師は生前、「一人一人の尊厳が尊重される共生社会を作ること」そして、「地域から発信するNGOの重要性」を語っていました。映像では、若林会長が住職を務める長野県安楽寺を中心とした地域の皆さまの活動や想い、その広がりをお伝えします。
登壇者紹介
島薗 進(しまぞの・すすむ)先生

上智大学大学院実践宗教学研究科教授、グリーフケア研究所所長、東京大学名誉教授、曹洞宗総合研究センター講師。
専門は、日本近代宗教史と死生学で、現代社会において果たすべき宗教の役割についても強い関心を持ち、多数の著書、論文などを執筆。
著書『日本仏教の社会倫理―「正法(しょうぼう)」理念から考える』(岩波書店、2013年)他多数。
オフィシャルサイト
http://my.spinavi.net/shimazono/
大菅 俊幸(おおすが・としゆき)様

シャンティ国際ボランティア会の専門アドバイザー、曹洞宗総合研究センター講師。
高校教員などを経てシャンティの創立者有馬実成師に共鳴し、NGOの世界へ転身。仏教精神に根ざした社会貢献活動を探求し、シャンティでは約20年間、国内事業や広報活動に取り組む。
著書『泥の菩薩―NGOに生きた仏教者 有馬実成』(大法輪閣、2006年)
『慈悲のかたち―仏教ボランティアの思考と創造』(佼成出版社、2017年)
『仏教の底力ー現代に求められる社会的役割』(明石書店、2020年)
第一部 東日本大震災から10年

大菅俊幸様(以下、大菅):こんばんは。今日は、こうして対談イベントにお越しいただいて、大変有難く思っております。また各地のみなさんとオンラインを繋いでのトークセッション対談ということで、文明の力もここまで来たんだなとおもいます。今、映像を観ましたが、地域の皆さまにシャンティは支えられてきたのだなと思いました。安楽寺さまには何度も通わせて頂き先代の若林順天老師とも親しくお話させていただき、懐かしく感じていました。島薗先生、映像をご覧になっていかがでしょうか?
島薗進先生(以下、島薗):非常に感銘を受けました。海外の支援活動がシャンティの第一のイメージでしたが、日本の地域社会の宗教の働きと密接に結びついているということがよくわかり、なるほどと思いました。
大菅:今日こうして島薗先生と対談できることを大変嬉しく思っております。実は一年前に予定しておりましたが、やっと実現出来ました。40年という節目にお迎えできてよかったです。
今日の会談への経緯を少しお話しします。2018年から2年間に渡って、『曹洞宗報』に「仏教の現代的社会的役割を考え直す」ということでインタビューを連載し、私にお声がけがありました。そこで島薗先生や川又俊則先生や前田伸子先生にお話を伺っての2年間に及ぶ特集が組まれました。お話の中で、幕末から明治にかけて日本の社会福祉、児童福祉の草分けとして活躍した福島の瓜生岩さんのことを教えていただき、非常に感銘を受けました。福島の会津で幕末から明治にかけて活躍され、戊辰戦争で敵味方関係なく救護活動を行い、その後、親を失った子どもたちの世話などを積極的に行っていた方です。日本の児童福祉・社会福祉の草わけと言われる方だと伺いました。その方が当時の仏教寺院、曹洞宗寺院のバックアップがあったからこそ活動が出来たということを知りました。その後、瓜生が立ち上げた「福島愛育園」の現在の理事長が福島市の曹洞宗円通寺住職、吉岡棟憲さんであることがわかりました。吉岡さんは元シャンティの理事でもあり、存じ上げているので、連絡をとったところ、喜んで下さり、有難くも、吉岡師にご案内いただいて、島薗先生と一緒に1泊2日で福島の北方から福島市にかけて瓜生ゆかりの地を訪ねることになったわけです。今回は40周年ということもあり、島薗先生にぜひ来ていただきましょうという話になりました。また、東日本大震災から10年目ですが.シャンティの40周年と結びつく、またコロナ禍から1年で迎えるというのも意味が深いと感じました。東日本大震災は、日本仏教にとっても大きな節目となったように思います。振り返ってみて改めて今どんなことを感じているでしょうか。
島薗:吉岡住職は、福島の原発事故の後にご自分でこども園をなさっていて、とても経営が難しくなってしまった。しかし、それに対する十分な支援もない状況で、色々な発信をされている。福島や宮城や岩手もそうだが、東日本大震災は地域社会の仏教の力が見直された。ある意味では、ふるさとが津波により、原発事故により壊された。それだけに失われたものの中に尊いものを思い浮かべたという事もあります。よく「ふるさと」の歌が歌われました。それと、仏教が持っている地域社会での精神的な模索、そのなかの、死者と共にあるわたしたち、ということも入っています。そんなことが思い起こされました。先ほどの福島愛育園も、瓜生岩という人は、あらゆる手段を使い活動をしました。浅草にも(瓜生の)碑があります。渋沢栄一にはたらきかけ、皇族や旧友の女性たちと協力しながら、また儒教的な考えがあるのかもしれませんが、キリスト教や神道とも協力したと思います。福島愛育園が残っているのは、仏教会と協力したからです。それも曹洞宗だけではなく宗派を超えての協力があったからです。有名な人物に、明治時代、岡山の石井十次というキリスト教徒がいます。岡山でも仏教徒が子ども支援などをたくさん行っています。瓜生岩は宗教を超えながら仏教を足場にしてこういうことを行ってきました。忘れられていた面もありますが、震災で思いおこされました。つらいことがあると、お寺に逃げ込むということがあった。津波で家を失った人もいた。人を失ったつらさをお寺が聞いてくれたということもあった。一方で、『寺院消滅』という本が出る。地域社会で寺院は厳しくなっている。と言われる反面で仏教が歴史の中で培ってきた重さが、思い起こされました。(震災には)仏教復興という側面があったと思います。
大菅:私も何度も東北の被災地に足を運びました。仮設住宅でのお茶会、傾聴活動に行ったとき我々もいましたが、一部の方はお坊さんのところに行って相談する光景が印象的でした。急に身近な人を亡くした方にとっては人間の死をどう考えれば良いかなど、お坊さんに対する期待感がとても強いことを感じました。改めて仏教、お寺、僧侶という存在が再認識されていたのではないかと思います。先ほど、生と死というお話がありましたが、様々な活動をしたなかでも、今回、急に身近な人を亡くした人にどう寄り添っていくかということが、大きなテーマとして初めての体験だったと思います。
2011年の7月に気仙沼事務所に女性が訪ねてきて、「弟夫婦が子どもを亡くして憔悴している。そういった親たちの集いの場をもって頂けないか?」と相談されました。その後、仙台の「自死遺族の会」と協力して、比較的早い時期に、「つむぎの会」という集いの開催までこぎつけることができました。その活動のサポートを少しお手伝いしているときに仙台の専門家から宗教者にも関わった方が良いとアドバイスをいただきました。それで知り合いの僧侶の方(岩手県一関市・曹洞宗寺院の住職)に関わっていただきました。やはりこれが大きかったです。宗教心をもっているかどうかが重要であること、宗教者(僧侶)に関わっていただくことがとても大切であることを実感し、今までになかった体験だと感じています。 そして、そのことが大きく思い起こされたのが東日本大震災だったのではないかと思います。
島薗:1995年にも阪神・淡路大震災があり、5000人以上の方が亡くなりました。そのときに「ボランティア元年」「心のケア」が広まりました。精神科医や臨床心理士の役割は目立ちましたが、宗教者の支援活動は目立ちませんでした。「ボランティアという誰でもできることを宗教者がやらなくてもよい」という声もありました。ところがその認識が変わってきた節目がありました。曹洞宗の青年会のお坊さんが行う「行茶活動」ですが、転機は能登の地震だったと思います。ここは總持寺祖院のお膝元でもあり、やはり寄り添いという事が大切だと若手の方々が認識したのだと思います。僧侶が聞き手になる。これが被災者の力になる。これは共に生き、僧侶の方はそこで学ぶ、共に学ぶ。という経験でもあったのではないかと思います。私ども上智大学のグリーフケア研究は2005年のJR福知山線の事故から始まりました。2008年から研究所も始まりました。これは看護師やケアを行う社会福祉士などの職種の方々が悲しみに寄り添うことは難しいが行わなければならない、と感じていることでグリーフケアの重要性の再認識が始まりました。これも時代と並行としていると思います。阪神淡路大震災の時はそんなに言われていませんでした。直感的な理解はあっても、どうすれば良いかわからなかったという事かも知れません。そこから傾聴や寄り添いという事が大事だとなり、そこに宗教の要素が大事だとなってきました。神戸は大都市ですが、東日本のときは地域社会で人々の宗教心が共に共有されています。その違いと時代の違いもあるのかもしれません。失われていく精神文化に若い人も気付くという流れもあったのかもしれません。そのなかに宗教的な考えも大事だという流れがあったように感じます。
大菅:私はシャンティに入職したのが阪神淡路大震災の少し後だったので、神戸にも行きました。あの頃から心のケアと言われてました。能登の方でも同じようだったと思いました。東日本大震災の後に、臨床宗教師ができました。非常に画期的に思えました。 島薗先生は、「日本臨床宗教師会」の会長さんでしたね。臨床宗教師が生まれたことについて、少しお話しいただけますか.。
〇なぜ、今、臨床宗教師なのか
島薗:わたしは宗教者でもないのに、まとめ役ということで「日本臨床宗教師会」の会長を、この3月で辞めますが務めてきました。これは遡ると、1970年ごろから、イギリス、アメリカで始まったホスピス運動というものがあります。これは「癌などで死にゆく人のケアをする。直すことはできない。しかし苦しんでいる人が目の前にいる。何をしなければならないのか」ということからスピリチュアルケアという言葉が出てきました。しかしこれは誰がやるべきことなのか、医療の方々もそういう事に関わらざるを得ません。キュアよりもケアなのだが、ケアの一番大事なところがわからない。特に死にゆく人のケアに足りないものがあるのではないか、よりよく死を迎えていただくために医療は何もできないのではないか、ということに医療関係者が気づいたのです。そしてスピリチュアルケアというものが必要だということになっていきました。しかしこれは誰がやるのか?キュアよりもケアなのだが、ケアの一番大事なところがわからない。そこでベーケン先生らが出てきて、次第にスピリチュアルケア的なもの、生と死を考える会が日本でも広がっていきました。そのなかでグリーフケアの重要性、日本ではチャプレンがいません。病院などの現場に必ず宗教者がいるのが欧米では当たり前ですが、そうではない中で、どうすればスピリチュアルな次元を日本社会でふさわしい形にしていけるか模索してきたと思います。でもなかなか形にならない。長岡西病院など形になった例もありますが、その様な状況で宗教・宗派をこえた横の連携が東日本大震災の後に自然に起きてきました。そういう宗教者の働き方は医療者の方や行政の方も協力しやすく、受け入れする側の人たちも抵抗感がありません。その元が岡部健先生でした。この方は2010年にガンにかかり、2012年に亡くなりました。遺言みたいになってしまったのですが、「医療だけではもたない。そこは宗教の役割だ。しかしそれは特定宗派の教義を説くということではない。」という日本版の、欧米とは違うあり方が生まれてきたということだと思います。その養成講座が東北大学にできまして、全国的に広がってきています。死に往く方々のケアを初め、災害時のケアなど弱い所に手が届くようなケアが、新しい形で広がるようになってきたのだと思います。
大菅:これは研修をして資格をとり臨床宗教師になっていくという事ですが、先ほど言われた「布教をするのではない」というのはどういう事なのでしょうか。
島薗:ひとつには、布教伝道をしてもらいたい訳ではない。つまり、しっかりとした信念をもってもらうということではなく、今自分が向き合っている死という人生の課題をどう整え良き過ごし方が出来るかという部分の支援です。ですから、まずは話を聞く「傾聴」という事だと思います。これはサイコセラピーのなかで大事だと言われてきたことですが、宗教的なことが有効になるのは、まずは話を聞くところから入っていることが大事だと納得されてきたと思います。
大菅:お話頂きありがとうございます。私も第7期をオブサーバーで受講させて頂き、本当に貴重な体験だったと感じております。今、島薗先生にお話頂きました「臨床宗教師」が東日本以降に誕生したことに大きな意味があると思います。1つは布教伝道ではなく、困難を抱えた人に寄り添う。それを大事にする。という発想が投げかけられていると思います。 もう1つは、宗教・宗派を超えての繋がりということだと思います。 そういう発想でやりませんか?という投げかけがあると思います。 臨床宗教師になるという事も大事ですが、それぞれの足りない部分を補う、そのメッセージを受け止めて、それぞれの場面で必要と思われる転換に取り組んでいくことが大切ではないかと思います。そういう意味で新しい宗教の扉が開いたのではないかと思います。
島薗:私も学校の教員で教える立場なので、どうしても上から目線になりがちです。答えはこっちが持っていると期待される場面もありますが、まずはわからない、あるいは共に感じるということ、その経験を積んで宗教者として、あるいは教員として相手から学ぶという、プロセスになってくると思います。
大菅:ありがとうございました。たくさんお聞きしたいところですが次の第2部のお話に入りたいと思います。設立40周年を迎えたシャンティということで、今日は私も含めシャンティの関係者にとって島薗先生がシャンティをどのようにご覧になっているのかと、どういうご助言をいただけるのか楽しみです。よろしくお願いします。
第二部 設立40年目を迎えたシャンティ
〇有馬実成師とは

島薗:寄り添うとか傾聴という、上から目線ではないという支援の在り方は、シャンティの有馬実成師が先駆的に持っていたものではないかと思います。まず1981年、なぜこの時期にまたシャンティがどのように始まったのか、有馬師の歩みという所からお話いただきたいと思います。
大菅:有馬実成さんは山口県周南市・曹洞宗原江寺前住職で、シャンティの初代専務理事だった、実質的創設者と言える方です。JANICの元理事長であり、NGO界のリーダーだった方です。昭和11年に生まれ、若い頃は地元山口県で、「禅の文化をきく会」という今でいえばカルチャセンターの走りのような、中央の文化人を呼び地元で講演をきくという会を始めた方です。地域の文化活動から初めていったということです。昭和50年「在日韓国朝鮮人の遺骨返還の運動」など、文化運動、市民運動に取り組んでいました。非常に人権という意識に強い方でした。その後、「全国曹洞宗青年会」の立ち上げに深く関わり、シャンティの前身である「曹洞宗東南アジア難民救済会議(JSRC)」の中心となって活動し、その活動を引き継ぐ形で、1981年に「曹洞宗ボランティア会」発足させました。それが現在のシャンティにつながり、2000年に64歳で亡くなられた。『泥の菩薩』を是非読んで頂ければと思います。曹洞宗の戦後のあゆみの中で、この方は重要な動きをしていたと感じます。
〇「慈悲の社会化」と「縁起社会の実現」―有馬師がめざしたもの
島薗:先ほどの明治時代の子ども支援の話が出ました。仏教NGOと言われますが、弱い立場の人々に対する支援活動と言われるものは、そんなに珍しいことではなかったようです。しかし、戦後の社会の中であまり目立たなかった。これは、1つは戦争で色々なものが途切れてしまったということがある。それから福祉国家ということで国がやることだという考え方があったかもしれません。もちろん宗教は1人1人の心の問題であるという事はわかりますし、それから親しい人や死者を見送り供養することは、これが檀家制度ともつながり仏教活動の焦点となっていると思います。本来の仏教の理念はプライベートなものだけではなく、共に生き共に学ぶということだったのではないかと思います。正法眼蔵の正法も正しダルマ(法)が社会に行き渡るということだったと思います。有馬師はそれを慈悲の観点から考えていたのではないかと、『泥の菩薩』を読むなかで感じましたが、いかがでしょうか。
大菅:<慈悲の社会化><縁起社会の実現>ということをよく有馬さんは言っていました。それがヴィジョンだったと思います。<慈悲の社会化>とはどういうことかというと、私の受け止め方ではありますが、「他の苦しみを我が苦しみとして、社会が抱える問題の解決のため、主体的に関わり、行動する。そして、その輪を広げること。気持ちだけではなく実際に行動していくこと」の大切さを力説していたと思います。そして<縁起社会の実現>とは、「一人ひとりの人間の尊厳と多様性が尊重され、やさしさと信頼に結ばれる社会を実現すること」で、仏教の理念を現代のなかで皆さんに伝えていくということをされたと私は受け止めています。
島薗:日本の仏教というと鎌倉仏教だと言われ、「曹洞宗であれば道元禅師、それから浄土宗、真宗でいえば法然・親鸞というような宗祖こそが精神的な基盤である」、ということにこそ日本の仏教の確信があるという捉え方もありますが、有馬師の場合は少し違う流れで捉え方をしていたのではないかと思います。いかがでしょうか。
大菅:そうですね。曹洞宗の宗侶としての誇りをもって生きて活動されていたとは思いますが、「現実に苦しんでいる方々にどうしたら良いか、そこにふさわしい仏教の思想があるのではないか。」ということをずっと考えていたのではないかと思います。そこで後ほどお話する叡尊の思想に出会う訳ですが、先ほどの臨床宗教師史の話にもつながりますが、教団教義ありきで向かっていく宗教者ではなく、現実の困難をどのように解決していくべきか、どのように仏教が役に立てるのかという関心だったと思います。そのなかで出会ったのが叡尊のエピソードだったと思います。ですから曹洞宗の宗侶としての誇りをもって生きつつも必要に応じてはどんな思想でも良いという、広いというより深い考え方のある方だったと思います。ですから若いころには上智大学にも通って神学の教義も学んでいましたし、一つの枠の中にとらわれない発想の方だったと思います。そこが私自身も惹かれる所です。
島薗:道元禅師も正法眼蔵随聞記などに、慈悲がいかに重要かお話されていますが、禅門の修行からは慈悲というものが具体的にどう生きてくるのか、くみ取りにくい訳です。もちろん有馬師は禅を極めたうえで道元禅師と同時代の叡尊がいたと、禅でも文殊信仰が重要ですよね。しかし叡尊、忍性は真言律宗といわれますが、この流れの文殊信仰は少し違うみたいです。その辺りを少し教えていただけますか。
大菅:有馬さんは講演の際や、原稿を執筆する際に必ずと言っていいほど取り上げていたのが叡尊の一説になります。ここに非常にこだわっていたように思います。その一説を紹介します。1269年(文永6年)、旧暦3月25日、叡尊は奈良の般若野という所に2,000人にも及ぶ大勢の人を集めて説法を行ったといわれます。集まった人たちは、叡尊の門弟や信者たち、貴族や武士たちも大勢いたが、圧倒的多数はハンセン病者など弱い立場にある人々でした。その時、次のように説法したといわれます。『文殊経』に、生きた文殊菩薩に出会おうとするならば、慈悲心を起こせと書いてある。なぜなら文殊菩薩が生きた姿でこの地上に現れるときは、貧窮孤独(ひんぐうこどく)の衆生の姿となって現れるからである。貧窮孤独の人たちに出会って、無関心であったり、忌避したりして慈悲心をもたない人は、文殊菩薩に出会いながらもついに出会えない。 さて、今日、般若野には大勢の貧窮孤独人々がいる。その人たちこそ、われわれに慈悲心を起こさせるために地上に現れ給うた文殊菩薩なのだ。こう語って、叡尊はハンセン病者などを入浴させ施食を行い、病の介護を行ったといわれます。ここに有馬さんは非常に心が打たれたのではないかと思います。このことを何度も書いたり話したりしていました。どういう考え方があるか私なりの受け止め方ですが、考えてみたいと思います。困っている人がいるから憐れみをほどこして助け、支援する。そうではない。貧窮孤独の人こそ生きた文殊である。その文殊に出会わせていただくために関わらせていただくのだ。貧窮孤独にある人こそ、人を解放し、人を生かす力を持っている。そのことを真剣に受けとめて、尊敬の心をもって関わらせていただくとき、こちらもその力にあずかることができる。という一つの思想があると思います。1980年、有馬さんたちがカンボジア難民キャンプに足を踏み入れた時、難民の姿から叡尊の一説を思い起こしたのだと思います。その時の話を何度も伺っていますが、このようなことだったそうです。カンボジア難民キャンプにもお寺があり、そこに日本から若い僧侶の方々(有馬さんたち)が行きましたが、カンボジアの人も仏教徒が多数で非常に信仰心が篤く日本からお坊さんが来たことに凄く喜ばれ、せっかくなのでご挨拶を、と声がかかったそうです。その時に挨拶した方が松永然道老師でSVAの初代会長です。その時、何を話せば良いか悩んだそうですが「何をすれば良いかわからないが、今日は皆さまの事が心配で来ました。」と話したそうです。挨拶を終えた後に、まずいことを言ってしまったのではないかと考えている時に、近くから長老の難民の方が寄ってきて「何もしてくれなくてもわざわざ私たちのために来てくださったことが嬉しい。今日は喧嘩が一件もなかった。それだけ皆さんが来ることを楽しみにしていた。」と話したそうです。そして、なけなしのミルクを布施したといいます。有馬さんたちは、いたく感激、頭を打たれるような衝撃だったと思います。つまり、こちらが助けるつもりで訪れたのに、逆にこちらが布施を頂いてしまった。その時に有馬さんは叡尊の一説を思い起こしていたのではないか、というのが私の推測です。つまり叡尊が示した、貧窮孤独の人に関わって文殊とまみえる、とはこういうことではないか、と思われたのではないかと思います。今、難民の姿を通して我々は文殊様の姿に出会ったのではないか、と思ったのではないでしょうか。その後、日本に戻ってから、有馬さんはこの体験をもとに難民支援を呼びかけています。その時の文章にも叡尊の話が引用されています。叡尊の話に心を打たれ、その後に難民キャンプで腑に落ちたのだと思います。ですから有馬さんの難民支援への決意は相当なものがあったと思います。実際の困難な現実に向き合うのに、どんな考え方が必要なのかを常に求めていたのだと思います。叡尊につながり、難民キャンプにつながり、今のシャンティにもつながってくる。また、今「共に生き、共に学ぶ」ということを理念として掲げていますが、このような体験が基になって積み重なって現代に来ているのだと思います。
島薗:今日はシャンティ40周年、有馬師が亡くなって20年という節目に有馬師の仏教の根本の様なところを印象的にお話いただきました。私は、これは現代人の心に響く話だと思います。普通の人がボランティアに行って感じることと非常に通じている、それを深みのある話としてお話頂きました。もっと伺いたい所ではありますが、そろそろ第3部に入りたいと思います。第3部はコロナの時代という事でお話していきたいと思います。
大菅:せっかく今、三輪空寂の話が出たので少しだけお話しします。有馬さんは、「仏教ボランティアは三輪空寂の布施である」とよく語っていましたが、まさに、そのことを難民の姿から学んだと思います。つまり、布施する側、布施を受ける側、布施物、その3つが対等に支え合う布施ということです。まさに、有馬さんは現実の出会いの中から三輪空寂を学び取ったのだと思います。これも「共に生き、共に学ぶ」という考え方がバックボーンにあると考えています。ですから仏教とは、支援活動ボランティアの根本にあるものを的確に表している宗教ではないかと考えています。
第三部 コロナ以後の地域社会とは
〇コロナ禍から宗教が学ぶもの

大菅:コロナ以後の地域社会という話です。コロナはこの一年で収まることなく東京でもまた増えてきています。また、山形や宮城では独自の緊急事態宣言も出されています。今までに無かったコロナ禍ということを通して、ここから宗教界が学ぶものについて、島薗先生にお話を聞いて行きたいと思います。
島薗:まず寄り添うということが2011年の3月11日以降、多くの方が考えたことだと思います。負担を共にしたいというある種の連帯感、これは災害ユートピアとも言いますが、お互いの気持ちが通じ合うように動きました。もちろん、原発事故は簡単には解決できない問題を投げかけましたが、お互いが助け合うという気持ちが広まりました。また、それが宗教と結びついて感じられたのですが、今回は寄り添うといっても近くに行けませんから、寄り添うという言葉とソーシャルディスタンス、という矛盾が生じています。例えば臨床宗教師会だと「カフェ・デ・モンク」が有名ですが、被災者が集まる所にお茶を持って出向き、打ち解ける場を作ることが難しくなりました。時間を共有することで心が開いていくという経験が難しくなり、宗教を掲げて集まることも難しくなりました。韓国などいくつかの国々で、宗教的な集いの場で規模の大きいクラスターが起こりました。そして、世界各地で礼拝などの宗教的な集いで人々が集まることを慎む傾向が強まりました。そういう意味では何をして良いか分かりません。その中、オンラインでなんとか乗り越えていけないかという明るい話題もありましたが、全体としてはとても辛い状況だと思います。特に死者を送る看取りが出来ない。親の見舞いにも行けない。お正月も帰れない。孫にも会えない。そしてお葬式でもお骨を1人で拾うということが起こってしまいます。これは2011年のあり方とは、とても違うと思う点です。宗教的スピリチュアルな支援が行き詰った感はあると感じております。自分自身も気持ちが塞ぎ込んでしまい、ある意味で振り返る時間を頂いたとポジティブに受け止めることもできます。しかし、人とつながることができなくなった、それも弱い立場の人ほど問題が難しく、世界的にも重苦しい問題を更に悪化させている様にも感じます。
大菅:私の身近な人たちの中にも、若い人をオンラインで繋げてサンガというネットワークを作るのに動いている方もいますが、檀家さんとの関係というよりもお坊さんと一般の方々をつなげていく活動を模索している方々もいます。新しい段階に差し掛かっているのではないかと思います。
〇小説『ペスト』から見えてくるもの
大菅:コロナ禍において、アルベール・カミュの『ペスト』という小説がずいぶん読まれているようですね。私も読みました。コロナ禍の現在というものがよく照らし出されてくるように感じました。先生も、この作品を通して論じていますね。この作品からどんなことが見えてくるでしょうか。
島薗:カミュはサルトルとも近い実存主義者で、不条理、意味が失われた世界に生きているという考えを強く持った人物で、あまり宗教と縁がないイメージでした。ところが、この作品を読んでかなり宗教に近いものを持った人物だと思いました。少し伝記を調べますと、アルジェリアの生まれで親はスペイン系の貧しい家柄だった。奨学金や高校の先生に助けられて大学に行けたという方でした。卒業論文はキリスト教について書いていました。この『ペスト』というのは、アルジェリアのオーランという町がロックダウンになり、何カ月も出られなくなったという話です。カミュ自身は感染症を経験したわけではありませんが、ナチス占領下でのフランスでレジスタンスに関わった経験はあります。 その全体主義的な支配にある状況とパンデミックな疫病で出口の見えない、人が見捨てられるように死んでいく状況に対して何もできないとう不条理、そういう状況についてカミュは書いています。それまでの作品にはない、最後にある種の希望のようなものが見える作品になっています。それは、ここに登場する神父が、当初、人々にひたすら悔い改めを説いていました。「人々の不信仰がこの苦難をもたらした。今こそ、その罪を悔い改め、神を信じ、すべてを委ねるべきだ。」と演説をするのです。それに対して、主人公である医師のひたすら苦しむ人々のために働く姿に共鳴し、ボランティア団体ができる。まったく罪のない子どもが死んでしまうといった状況をみて、神父もボランティアとして支援活動に加わるようになります。「悔い改めると言っている時ではない。目の前の苦しんでいる人に何が出来るのか、そういった生きた人間から出発するべきだ。」という話です。不条理を良く自覚した人たちがボランティア活動に参加し始める話です。こういう精神は現代にも繋がっているのではないか、何が出来るか分からないが出来ることをしよう。それが共に生きる。この作品では友情として描かれています。そこに希望があります。第2次世界大戦で露わになった、人間の醜い面や弱さから見えてきた希望を語っていますが、それがコロナ禍の現代人にも通じるところがあるのではないかと思います。
大菅:私もとくに神父さんの姿がとても印象深かったです。ペストにさいなまれた町の人々に対して、最初の説教は「神の罰」などと述べて、厳しい調子がありました。しかし、1人の少年のむごたらしい死を目の当たりにすることで変わりました。率先してボランティアに加わって、ペストに感染した人の場所から離れることはありませんでした。むしろ、ペストの危険に身をさらしているようでもありました。そして、その後に行った2回目の説教も1回目とはがらりと変わっていました。「あなたたち」ではなく、「私たちは」と言うようになっていました。神父の中に変わったものがあるのだと思います。それこそ宗教者として距離を置くのではなく、一緒に苦しみ、一緒に行動するという視線に変わったのだと思います。その部分を読んで、有馬さんが言われたことはこういうことなのかなと思いました。有馬さんは晩年、「私たちは市民にならなければならない」と、特に阪神淡路大震災の頃によく言っていました。「日本人は政府や行政にどうも依存してしまうが、市民でいなければならない。あるいは市民意識を持たなければならない。」とよく言っていました。有馬さんが言う市民とは、社会が抱える問題を我がこととして捉えて、主体的に行動する人のこと、もう一つは、自分の尊厳を知る人だと言っていました。「自分の尊厳を大切に出来る人は他人の尊厳も大切に出来る人である。また、お坊さんも宗教者である前に市民でなくてはいけない。」という事です。お坊さんは歴史的に市民になる機会を失っていた。という話をどう理解すればよいかと考えましたが、『ペスト』の神父の変化を見てこういうことを言いたかったのではないかと思いました。大衆と自分たちは違うということではなく、飛び込んで一緒に行動する宗教者でなければならない、ということを言いたかったのではないかと思います。カミュという人は、キリスト教の勉強もしていたと伺いましたが、従来のキリスト教でもなく社会主義でもなく、その間にある第3の道を目指していたであろうと翻訳者の方が解説に書いていましたが、有馬さんも非常に似たところがありました。従来のような教団の仏教でもなく、普通の市民社会運動でもない、第3の道を目指して作ってきたのがシャンティなのではないかと思います。その在り方はコロナ禍において新しい時代に相応しい形があるのではないかと思います。自画自賛になってはいけませんが、シャンティの存在意義が増してきているのではないかと感じています。もうひとつ、先ほど自分の内面を見つめる良いところもあるのではないかと言いますが、そういう意味でもシャンティの立ち位置が重要になってきているのではないかと思います。
大菅:コロナ禍で問われているのが医療などですが、その中で人間の意識なども問われているのではないかと思います。「本当の幸せとは何か」「生きる意味とは」「生と死はどのように決まるのか」など、内面についての関心が高まるといわれます。そして、新自由主義の影響でこれまで軽視されてきた宗教、哲学、文学なども再認識されるともいわれます。文学ということですと、物語や小説が人間の内面に及ぼす働きは大きいと考えられますが、それはシャンティが40年間追及してきたことでもあります。やはり外側だけ求めることに疲れはじめており、このままだと人間も地球も危ないかもしれません。内側の豊かさを求め始めているし、そうしていかなければならないと思います。シャンティが身体の栄養だけでなく心の栄養も大切という考え方を今日まで大切な考え方として活動してきている意義が、コロナ禍において次の段階に差しかかり、図書館活動などが素晴らしい意義をもっているということを再認識して取り組んでいく時ではないかと考えています。
島薗:今、色々な仕事がリモートでできるようになってきましたが、医療や介護、保育などリモートに出来ないケアの仕事などがあります。本当に大事なことが、いくら富があろうとも1人1人がケアしケアされる関係が貧しければどうにもならない。「神父が正しいことを言うが、1人1人をケアする。そのことこそが生きがいである。エッセンシャルワーカーという仕事がつらい仕事として注目されがちだが、一番重要な仕事でもある。」ということもコロナ禍で感じた大事なことではないかと思います。絵本について、私どものグリーフケア研究所で少年院に絵本の読み聞かせに行くと、普段あまり絵本を読まない若者たちが、読み聞かせで深く心を動かされると言われます。絵本や童話などは、近代人が大きなことをしようとして見失っていることを気づかせてくれる。そういうことかもしれません。シャンティが図書館活動でスマホで読める絵本などが活動のなかで見い出せてきているのは、有馬師の精神が新たな形で活かされているのかと思い、大変心強く感じています。
大菅:今日は地域社会を考えるというテーマで、話をしてきました。日本の地域社会の現状を考えると、海外と比べると社会的孤立度が高いということがいろんな角度から見えます。やはり身内だけを大事にするのではなく、見知らぬ人にも声をかけて大事にしていく地域社会が必要だという事を非常に強く感じています。2年前の台風の際、台東区の避難所でホームレスの方が拒否されたことがありました。それが日本の地域社会の現状なのかと思ったときに、地域に根差した宗教者の方々のこれからの大切な役割、思いやりの能力をいかに地域の人たちが育むことができるか、高めることができるか、地域の活動を通して期待されることが大きいと思います。先ほど宗務総長様よりお話がありましたが、「曹洞宗とシャンティとが、より一層協力をしていきましょう。」ということで協定を結びました。コロナ禍ではありますが、これから連携して新しい方向を見つけていきたいと思います。
島薗先生、今日はどうもありがとうございました。
島薗:ありがとうございました。
閉会のご挨拶
シャンティ国際ボランティア会副会長 神津 佳予子
今日はとても崇高で心が洗われる、そして厳しいコロナ渦をどう人間として生きぬしていくか、或いはNGO、仏教がどうあるべきかというお話を伺って、改めて決意を新たに致しました。
本当に長い間、皆さんにご支援を頂いて、一人ひとりの暖かいご支援、各関係団体の曹洞宗をはじめとして、宗教宗派を超えた支援を頂いていることを、本当にありがたいと思っていて、その力なくしてはこの40周年というのは実現いたしませんでした。
私たちはシャンティの理念を大切にしながら、これからも皆さんと一緒に歩んでいきたいと思います。

設立40周年記念対談イベントは盛会のうちに終了となりました。
地球市民事業課 渡邉・村松